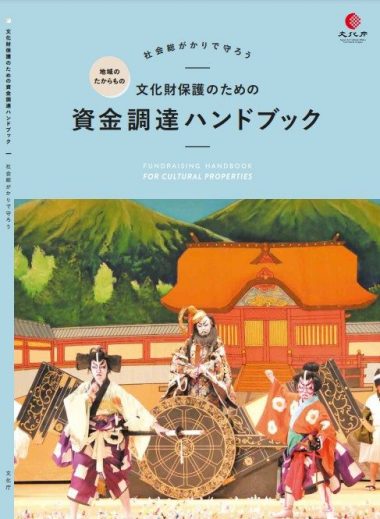令和6年能登半島地震 文化財復興 緊急支援|文化財サポーターズ >>
つまづく文化財の維持継承
- 所有者や支え手の少子高齢化で文化財の担い手がいない
- 文化財の維持費だけで経費が積もるばかりで、負担が大きい
- 文化財の大規模修理を控えているが資金の捻出が困難
- 結果、解体、滅失、散逸等の危機に瀕している
- ノウハウがない
- 地元が冷たい
- 行政が思考停止だ
等、文化財所有者らの悲痛の声が身近に聞こえてくる。なかにはすでにあきらかにギブアップした文化財も多い。
保存と活用の併走に必要な要素・・・理想は
- 自助による資金確保
- 互助による資金確保
- 地域住民等の積極的な関与
- 管理体制の確保
これがむずかしいなら、
CFで文化財所有者らの負担を軽減・・・そんな簡単ではない
これまでは、ある一定のコミュニティ(地域コミュニティや文化財保有会) など地有志有志でしか支え合うことがなかった中で、SNSやソーシャルメディア等の普及は同じ価値観の中で共感し支え合う(=お金を出し合う)仕組みを後押ししている。そのひとつがクラウドファンデイング。これを文化財保護・活用に応用することで、文化財所有者らが抱える課題を解決しようという試みを文化庁が冊子にした。つまり文化庁の官予算ではとても足らないとのこと。
文化財保護のための資金調達例
- 指定寄附金制度・・・寄附した法人・個人が税制上の優遇、ただし国指定文化財が対象
- クラウドファンデイング・・・群衆 (crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語
- ふるさと納税・・・使い道指定型もあり
- 企業版ふるさと納税・・・国が認定した地方公共団体のプロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に,法人関係税から税額控除する
- コンセッション・・・公共施設の運営権を民間事業者に設定する方式
- 地域活性化ファンド・・・地域の経済成長を牽引する事業者を支援するため、金融機関等と共同するファンド
- その他(指定管理者制度・不動産信託・修理観光/修理ライブ・宿泊施設活用等)
これまで接点のなかった遠い場所に住んでいる人が、文化財の継承に一役担ってくれることも可能な時代となってきたのは朗報。日本人アイデンティティがためされているともいえるが、もっと自然な支援の方法もあっていい。
文化財+観光+まちづくりのセット戦略・・・やはり特効薬は観光?
文化庁曰く「保存と活用の均衡を図りながら、文化財が地域社会・経済にまで深く貢献し、その成果が地域にも文化財にも適切に還元されるような」夢のような好循環の実現を目指すとあります。↓ご覧ください。
2016-17文化財を中核とした観光拠点形成による経済活性化調査研究>>
クラウドファンディングの仕組み
- 主催者が要望をクラウドファンディングサイトに掲載
- サポーターがサイトを見て、コメントやお金の支援
- 目標金額に達した場合、リターン品が支援者に送られるかも
無償の愛の提供に対する基本的な欲求は人皆持っているはず。テクニックも必要だが真摯に地道にトライしましょう。
「文化財の保存修復」に関する助成・助成団体
株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)
地域経済・産業の成長や新陳代謝による地域経済の活性化を目的の官民ファンド。地方銀行や信用金庫とREVICが共同で運用する地域活性化ファンドからの投資により、歴史的建造物などを観光資源として活用する取組が見られる。
アフターコロナに照準を当てまずは、「観光産業支援ファンド」はいかがでしょうか?安直ですが、起死回生には手っ取り早い。新たな観光資源の掘り起こしや、施設のポテンシャル発掘等、再生請負人らの技量によるところが大きいがもう失うものなどないなら、考えどころ。REVIC活性化ファンド業務>>
古いのに新しい! リノベーション名建築の旅
2019/5/22
リノベーション建築には、これらの歴史ある建築物ならではの味わいがぎゅっと詰まっている。
日本全国のリノベーション建築から22例を厳選。
読んで、旅して、リノベーション建築の真髄を味わえる、日本初のガイドブック!
先端技術による文化財活用ハンドブック
文化庁地域文化創生本部では,全国の自治体担当者や文化財所有者に向けて,先端技術による文化財活用ハンドブックを作成しています。